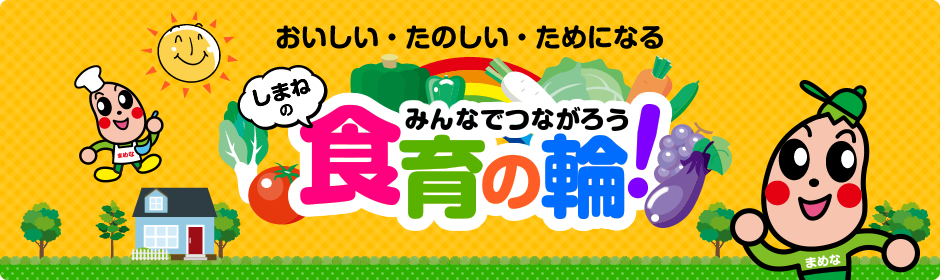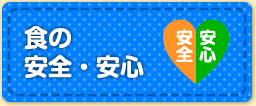離乳食のポイント
離乳食の進行に応じて、食品の種類及び量を増やしていきます。
1)食品の種類と組合せ
- 離乳の開始は、アレルギーの心配の少ないおかゆ(米)から始めます。
- 新しい食品を始める時には離乳食用のスプーンで1さじずつ与え、子どもの様子をみながら量を増やしましょう。
- 慣れてきたらじゃがいもや人参等の野菜、果物、さらに慣れたら豆腐や白身魚、固ゆでした卵黄など、種類を増やしてみましょう。
- 離乳が進むにつれ、魚は白身魚から赤身魚や青皮魚へ、卵は卵黄(固ゆで)から全卵へ、食べやすく調理した脂肪の少ない肉類、豆類、緑黄色野菜などの野菜類、海藻とヨーグルト、塩分や脂肪の少ないチーズと新たな種類も増やしてみましょう。
- 脂肪の多い肉類は少し遅らせましょう。
- 離乳食に慣れ、1日2回食に進む頃には、穀類(主食)、野菜(副菜)・果物、たんぱく質性食品(主菜)を組み合わせた食事にしましょう。
ヒント
家族の食事から調味する前のものを取り分けたり、薄味のものを取り入れたりすると、食品の種類や調理方法が多様になります。
鉄分について
- 母乳育児の場合、生後6か月頃に鉄欠乏やビタミンD欠乏の報告があることから、適切な時期に離乳を開始し、様子をみながら鉄やビタミンDの供給源となる食品を意識的に取り入れることが重要です。
- 生後9ヶ月以降は、鉄が不足しやすいので、赤身の魚、肉、レバーを取り入れ、調理用に使用する牛乳、乳製品の代わりに育児用ミルクを使用するなど工夫します。生後9ヶ月になっても離乳が順調に進まない場合や、適当な体重増加が見られない場合には、医師に相談した上で、必要に応じてフォローアップミルクの活用も検討しましょう。
- 牛乳を飲用として与える場合は、鉄欠乏性貧血の予防の観点から、1歳を過ぎてからが望ましいです。
2)調理形態・調理方法
離乳の進行に応じて、食べやすく調理したものを与えましょう。
子どもは細菌への抵抗力が弱いので、調理を行う際には衛生面に十分に気を配りましょう。
- 食品は、子どもが口の中で押しつぶせるように十分な固さになるよう加熱調理し、初めは「つぶしがゆ」とし、慣れてきたら粗つぶし、つぶさないままへと進め、軟飯へと移行させます。
- 野菜類やたんぱく質性食品などは、始めはなめらかに調理し、次第に粗くしていきます。離乳中期頃になると、つぶした食べ物をひとまとめにする動きを覚え始めるので、飲み込み易いようにとろみをつける工夫も必要になります。
- 調味について、離乳の開始時期は、調味料は必要なく、離乳の進行に応じて、食塩、砂糖など調味料を使用する場合は、それぞれの食品のもつ味を生かしながら、薄味でおいしく調理します。油脂類も少量の使用としましょう。
離乳の完了
離乳の完了とは、形のある食物をかみつぶすことができるようになり、エネルギーや栄養素の大部分が母乳、粉ミルクや乳児用液体ミルク以外の食物からとれるようになった状態をいいます。
- その時期は生後12~18か月頃ですが、母乳、粉ミルクや乳児用液体ミルクを飲んでいない状態を意味するものではありません。
- この頃には1日3回の食事、1日1~2回の間食となります。