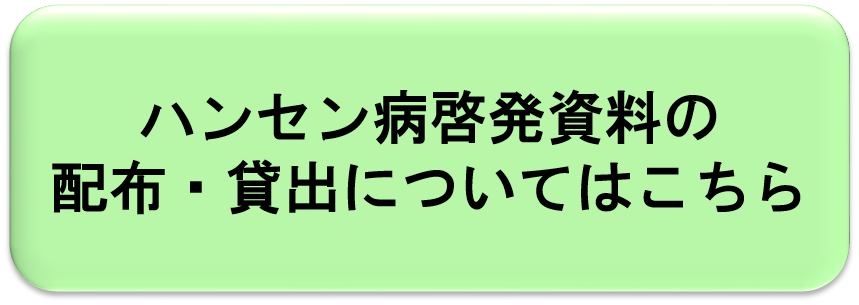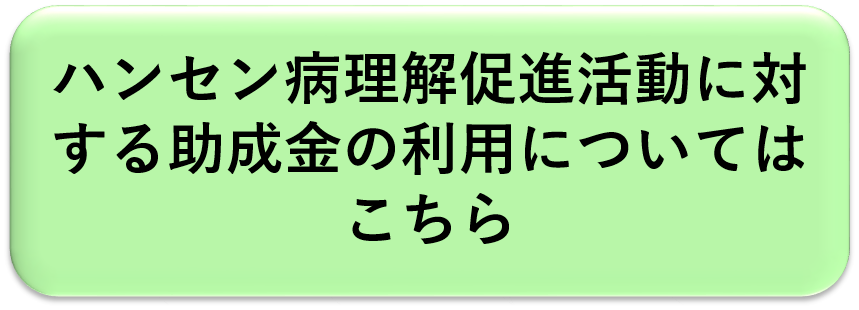■ハンセン病を正しく理解しましょう
ハンセン病という病気について、正しく知っていますか?
現在の日本ではハンセン病にかかる方はほとんどなく、また、発病しても薬で治すことのできる病気です。
しかし、古来からハンセン病の患者の方やその家族は厳しい差別を受けてきました。
・病気がわかると療養所へ強制的に連れて行かれ、病気が治っても療養所を出ることができない。
・家族と一緒に暮らすことができない。
・結婚しても子どもを産むことが許されない。
・家族への差別を避けるため、実名を名乗れなかった人が多くいる。
・今でもなお亡くなった後も故郷のお墓に埋葬しもらえない人がいる。
どうしてこのような事が起きてしまったのでしょうか?
ハンセン病について一人一人が正しい知識と理解をもち、差別や偏見の無い社会にしていきましょう。
ハンセン病問題の啓発に関するお知らせ
ハンセン病について
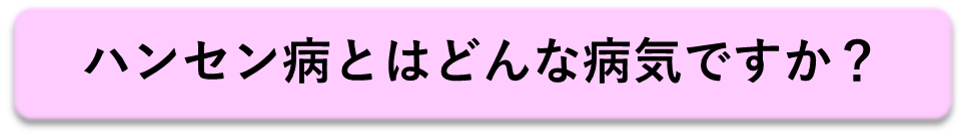
ハンセン病とは、「らい菌」に感染することで起こる慢性の感染症です。発病すると、知覚が麻痺したり皮膚に変化が起こったりします。現在は薬により治療することできますが、早期に適切な治療を行わない場合には末梢神経に障がいが起こり、痛い、熱い、冷たいといった感覚がなくなったり、顔や手足に変形が生じ、後遺症として残ることがありました。
かつては「らい病」とも呼ばれていましたが、現在は「らい菌」を発見したノルウェーのハンセン博士の名をとって「ハンセン病」と呼ばれています。
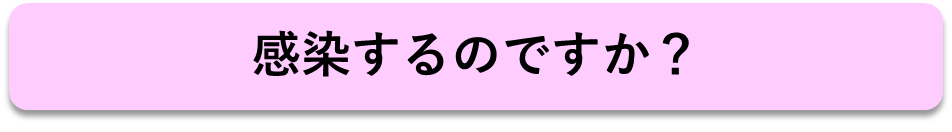
ハンセン病の原因となる「らい菌」は非常に感染力の弱い菌です。そのため、多くの場合、体の免疫力により「らい菌」は排除されます。免疫力の弱い乳幼児期などに多量の「らい菌」に繰り返し接触した場合には感染することがあると考えられますが、感染した場合でも必ず発病するわけではありません。衛生状態が悪い場合などには発病することがありますが、現在の日本の衛生環境下でしたら発病の心配をする必要はありません。
療養所で働いていた医師や看護師などの職員の中に、ハンセン病を発病した人が今まで一人も確認されていないことからもハンセン病が非常にうつりにくい病気であることが分かります。
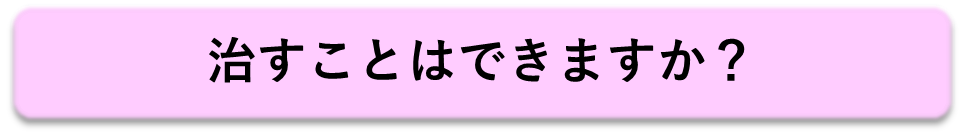
ハンセン病は薬で治すことのできる病気です。
かつては「不治の病」とも考えられていましたが、1947年に登場したプロミンという薬により治る病気となりました。現在は、いくつかの薬剤を組み合わせた療法が広く行われ、早期発見と早期治療により後遺症を残すことなく確実に病気を治すことができます。
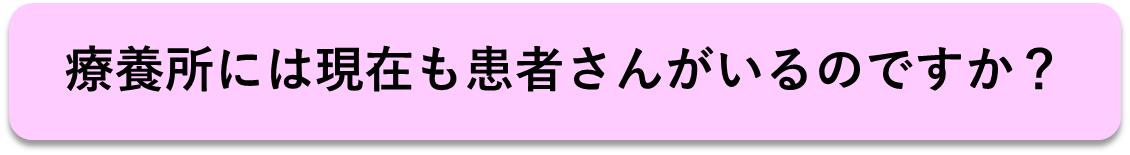
療養所に入所している方々のハンセン病は既に全員治っています。
しかし、皆さん高齢なうえ、ハンセン病による後遺症としての障がいがあることや、隔離政策によって長きに渡り療養所で生活してきたため社会に生活基盤がほとんどないこと、そして一般社会に未だ根強い偏見が残っていることなどから、社会復帰ができず現在も療養所で暮らしている回復者の方も多くいらっしゃいます。

かつては治らない病気とされていたこと、また病気が進行すると手足や顔といった人目に付きやすい部分に変形が生じるといった後遺症が残ることから恐れられてしまいました。
更に国が定めた「らい予防法」に基づく隔離政策により、警察や保健所などが患者の方を強制的に療養所へ収容する様子が、ハンセン病は怖い病気だという「誤った知識」を社会に根づかせ、ハンセン病に対する偏見や差別が大きくなった原因のひとつとなりました。
この隔離政策はハンセン病が薬で治る病気となった後も平成8年まで続けられました。そして、「らい予防法」が廃止された今もなおハンセン病に対する誤解や偏見が社会には残っています。
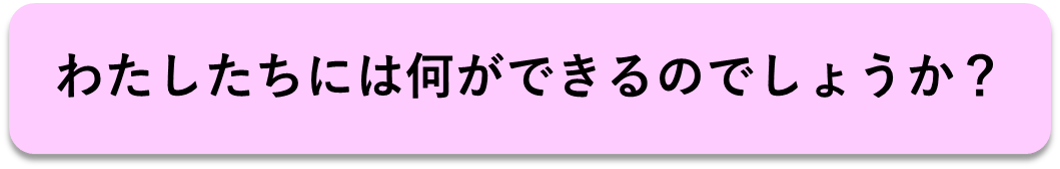
差別や偏見を無くしていくために、まずはひとりひとりが病気について正しく理解しましょう。ハンセン病に限らず、どのような病気であっても、病気であるということを理由に人を差別してはいけません。
そして、ハンセン病問題と同じことを二度と繰り返さないように、ひとりひとりが自分の立場でしっかりと考え、皆が共に生きる仲間として支え合っていくことが大切です。
療養所の現在
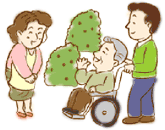
令和3年度現在、全国13カ所の国立療養所と1カ所の私立療養所に1,004名の方が入所しています(令和3年5月1日現在)
近年は、施設整備が進み、より安全で快適な療養生活ができるようになっています。
また、現在は地域に開放された施設となっており、見学者も多く訪れています。敷地内に保育園や一般の老人ホームの立つ療養所もあります。
「らい予防法の廃止に関する法律」等について
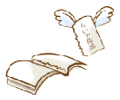
「らい予防法」は、明治40年の法律第11号にその源を発し、感染症対策としての患者の隔離を主体とした法律であり、患者隔離によりハンセン病の予防を図ってきました。
しかし「らい予防法」は、『感染しても発病することは極めて稀な病気であること』、『仮に発病しても治療方法の確立している現在では適切な治療を行うことにより完治する病気である』という医学的知見にそぐわなくなったにもかかわらず、見直されず存在し続けました。これらの結果、長い間ハンセン病患者及びその家族の方々の尊厳を傷つけ、多くの苦しみを与えることになりました。
このようなことから、平成8年4月1日に「らい予防法」が廃止され、同時に国立療養所の入所者に対する医療及び福祉の処遇の維持継続を図ることを目的とした「らい予防法の廃止に関する法律」が施行された後、平成13年6月には「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」が施行され、補償金の支給や名誉回復が図られることとなりました。
さらに、平成21年4月には「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」が施行され、ハンセン病患者であった方々の福祉の増進と名誉回復に向けた一歩を踏み出すこととなりました。
その後、令和元年には、ハンセン病元患者家族も国の隔離政策により偏見や差別の対象となり、多大な被害を受けたとして補償金を支給する「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が施行されるとともに、「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律」が施行され、国は、元患者家族の名誉回復や家族が置かれた境遇を踏まえた人権啓発、人権教育の普及啓発強化に取り組むことを約束するなど、さらなる一歩が踏み出されたところです。
お問い合わせ先
健康推進課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務所は松江市殿町2番地 島根県庁第2分庁舎3階にあります)
・療養企画係/療養支援係(被爆者対策、肝炎医療費助成、ハンセン病対策、調理師・栄養士免許など)0852-22-5329
・難病支援第一係/難病支援第二係(指定難病、小児慢性特定疾病など)0852-22-5267
・健康増進第一係/健康増進第二係(食育、歯科保健、生活習慣病予防、たばこ対策、健康増進など)0852-22-5255
・子育て包括支援スタッフ(母子保健、不妊治療費助成など)0852-22-6130
・国民健康保険係/医療保険係(国民健康保険、保険医療機関及び保険薬局の指導など)0852-22-5270・5623
・がん対策推進室(がん対策の推進及び総合調整)0852-22-6701
FAX 0852-22-6328
Eメール kenkosuishin@pref.shimane.lg.jp